済生会新潟県央基幹病院&崇徳会加茂病院のカウンセラー&院内相談員(MSW)増員!!!!

済生会新潟県央基幹病院&崇徳会加茂病院のカウンセラー&院内相談員(MSW)増員!!!!
- 提出先:新潟県済生会吉田俊明支部長、済生会新潟県央基幹病院遠藤院長、新潟県臨床心理士会藤沢会長、NPO法人新潟トラウマ治療協会、新潟県医療ソーシャルワーカー協会、花角英世新潟県知事、にいがたくらしごとセンター新潟オフィス、新潟日報社佐藤明代表取締役社長、滝沢亮三条市長、医療法人崇徳会加茂病院富所隆院長

作成者:#あきらメンヘラでも生きていきたい
活動詳細
■ はじめに(活動の目的や概要)
【院内カウンセリングや心理検査、患者(当事者)・家族は待ったなし】
特に、「自死率ワースト2位」の新潟県の精神科・心療内科の充実は'待ったなし'です。また、新潟県内は「お医者さんの充足度がワースト2位」のみならず、「カウンセラーや院内相談員(MSW)の充足度もワースト」です。
特に多くが、新潟市内など「都市部」に集中しており、郊外はさらに「人手不足」が否めません。
「うつ病」、「依存症」、「パニック障がい」、「人格障がい」、「発達障がい」、「てんかん」、「摂食障がい」、「強迫性障がい」、「統合失調症」、「不安症」、「PTSD」、「認知症」、病気ではない「HSPスペクトラム(繊細さん)」 と…メンヘラ(脳みそ系の問題)を幾重にも抱えやすい新潟県民。
これらを解消するには脳みそホルモンの「セロトニン」が欠かせません。しかし新潟県は地域気候上、この「セロトニン」の分泌が難しい地域なのです。
また、俗にいう「絆のホルモン」である「オキシトシン」は新潟県内の超過疎少子高齢化に伴い、また「個の多様性」が保ちにくい地域柄、分泌が難しいのです。
ここ最近は、新潟県内でも「精神科・心療内科」は'右肩上がり'ですが、肝心の「専門家」-「カウンセラー(臨床心理士)」、「院内相談員(MSW)」は足りません。
■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
【人材は都市部に集中。結局そこに頼るしかない!?】
こうした「専門家」の多くが利便性の高い「都市部」へ集中し、郊外は「人手不足」がぬぐえません。郊外にも特に「病院内」に人材を充実させるしかありません。
私たち、「当事者(患者)」や「家族」はやむを得ず、片道1時間以上の時間とその対価(お金)をかけて他地域、はてまた県外の専門家に頼るしかありません。
人材充実して、安定的に検査やカウンセリングができるようお願いします。
■エールの使用法
ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
それでももし頂けるようでしたら、お気持ちに感謝し、大変ありがたくお受け取りさせて頂きます。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。
【需要が右肩上がりの「精神医療」へ積極的投資を!!!!】
繰り返しですが、今新潟県内の医療業界は「大ピンチ」です。一部の中枢病院は県や市からの「税金」で赤字分の解消にやっきです。
病院を存続させるためには、やはり需要が右肩上がりの「精神医療」へ積極的に投資すべきです。
診療報酬改定に伴い、「児童思春期支援指導加算」と「心理支援加算」が精神医療分野で加わりました。
「児童思春期支援指導加算」は「発達障害支援法」の目玉である「早期発見・早期相談」を強化させるため、主に通院中の未成年の患者さんを診察するための加算です。
「心理支援加算」は「カウンセラー(臨床心理士)」に似た「公認心理士」による保険適用院内カウンセリングを強化するための加算です。
どちらにせよ、「カウンセラー(臨床心理士)」と「院内相談員(MSW)」を増員させ、積極的に精神医療へ投資しないと難しいのです。
【皆さんのお力が必要です】
改めまして、私自身SNSが苦手な体です。(´・ω・`)
今一度応援・拡散よろしくお願いします。<m(_ _)m>
■ 団体(代表)プロフィール
新潟県在住の30代女性。ASD(自閉スペクトラム症)+HSS型HSP(興奮+繊細)の併存当事者。「子ども発達障がい支援アドバイザー」(発達凸凹アカデミー)、「子育て心理アドバイザー」(一般社団法人子どもの育ちと学び)、「アンガーマネジメントベーシック」(日本アンガーマネジメント協会)有
新着報告
2026/01/06
募集期間延期
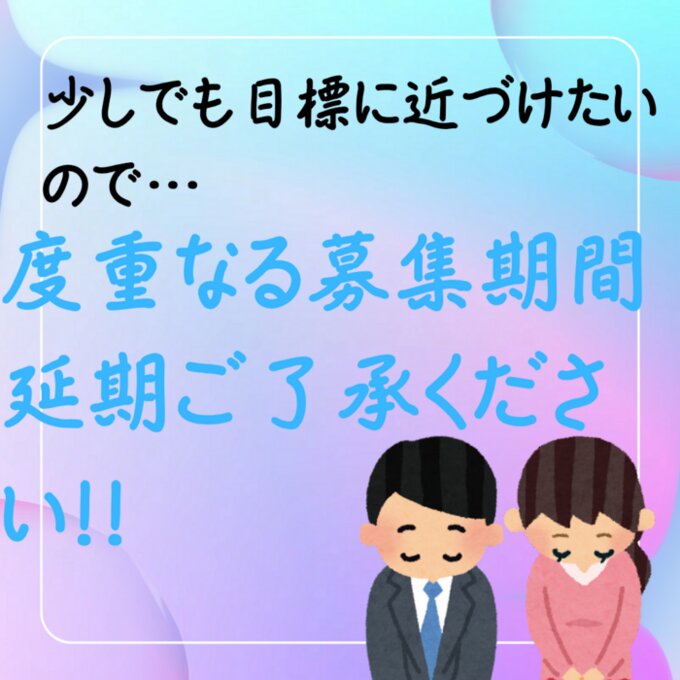
【度重なる募集期間延期、ご了承ください】
なかなか目標達成には至りませんので、募集期間を延期します。
度重なる延期をご了承ください。<(_ _)>
メッセージ
2026/01/07

峰田 はるか
世界有数の異常な政治による犯罪国、日本。なぜこのようになったか? たぶん仏教伝来以降の中国人支配が原因と考えられている。確かに日本の首相の日本人率?は、わずか2%と知られた。だから中国製メガソーラーで日本破壊が進んでいると考えると、納得?が行く。どうしますか?この異常な政治を!!
2025/07/09

小林 隆昌
自閉スペクトラム症と二次障害のうつ病で治療を受けながら働いています。この障害がもっと世の中に理解されるといいなと思います。活動応援しています。
2025/05/17

山本暖空
頑張ってください!
2025/01/16

原沢拓也
カウンセラーを増やして
悩みのある人が安心して暮らせるような世界にしましょう